デンタルニュース
インプラントを長持ちさせるには?自宅ケアと定期メンテナンスのポイント
日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。
インプラント治療は「しっかり噛める」「見た目が自然」と多くの方に選ばれていますが、治療が終わってからのケアが何よりも大切です。
どんなに丁寧に治療をしても、メンテナンスを怠ると炎症が起こり、せっかくのインプラントを失ってしまうこともあります。
私は歯科衛生士として、メンテナンスを続けて10年以上快適に使われている方を多く見てきました。逆に、数年でトラブルが起きてしまう方も…。
この記事では、インプラントを長持ちさせるための毎日のケア方法と歯医者でのメンテナンスのポイントを、わかりやすく解説していきます。
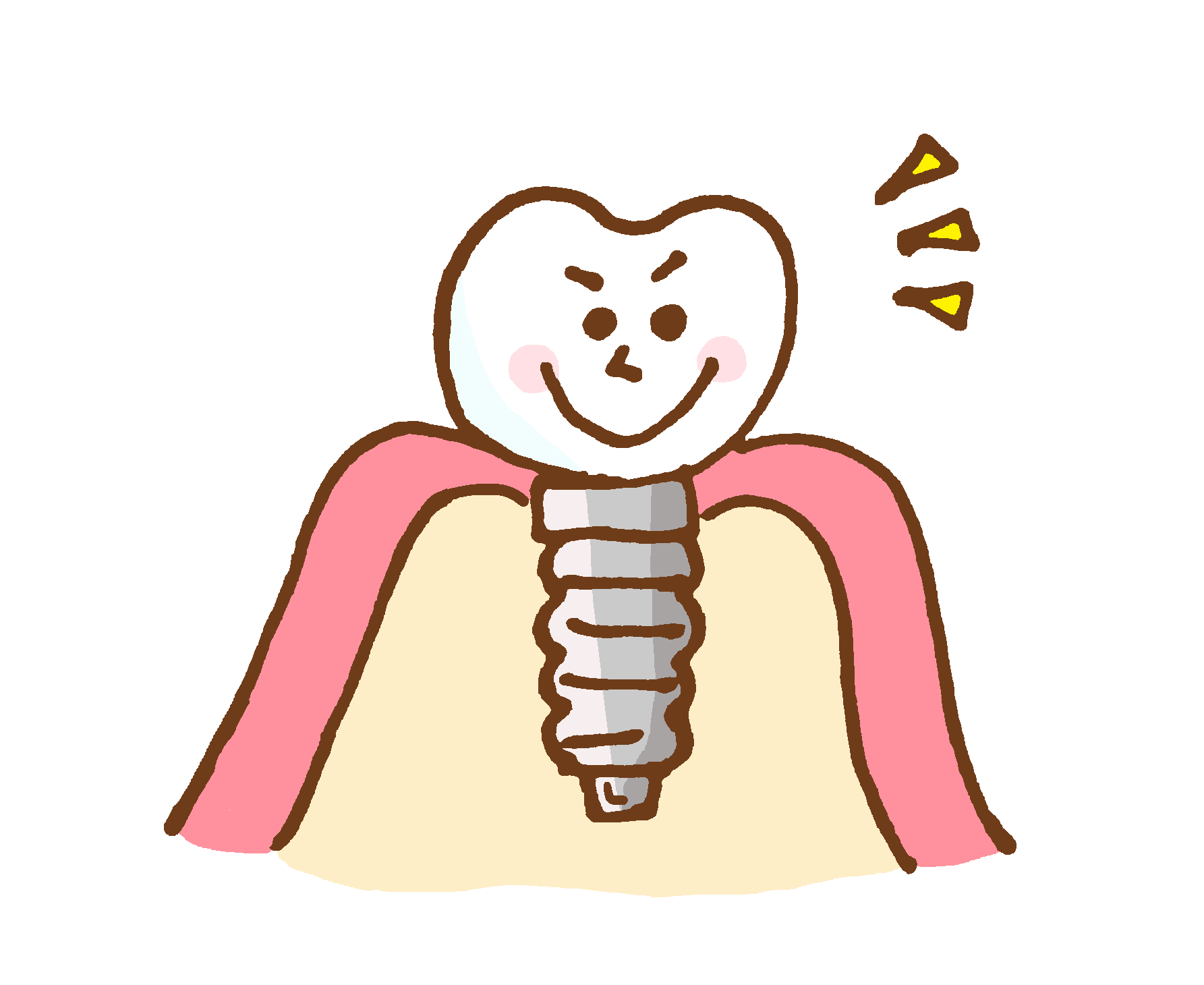
なぜインプラントのメンテナンスが大切なの?
①インプラントは「入れて終わり」ではない
人工歯でも歯ぐきや骨は生きている
インプラント自体は人工物ですが、それを支える歯ぐきや骨は生きています。
そのため、清掃を怠ると汚れや細菌がたまり、周囲の組織に炎症が起きてしまうことがあります。
私はよく患者さんに「インプラントも植木と同じです」とお話ししています。
根(インプラント)をしっかり支える土(歯ぐきと骨)が元気でないと、どんなに立派な歯でも長持ちしません。
メンテナンスを怠るとインプラント周囲炎に
インプラントの周囲に炎症が起きる病気を「インプラント周囲炎」といいます。
歯周病と似た症状で、歯ぐきの腫れや出血から始まり、進行すると骨が溶けてインプラントがぐらつくこともあります。
「痛みがないから大丈夫」と思って放置してしまう方もいますが、症状が出るころには進行しているケースが多いです。
実際に診療の現場で患者さんを診ていても、定期的なケアを続けている方ほどトラブルが少ないと実感しています。
②定期的なメンテナンスで寿命が大きく変わる
メンテナンスを続ける人としない人の差
インプラントはしっかりケアをすれば10年以上快適に使えますが、清掃を怠ると数年でトラブルが起きることもあります。
同じ医院で定期的にクリーニングを受けている方は、10年たっても問題なく使えているケースが多く見られます。
一方、メンテナンスをしないまま数年経つと、歯ぐきが下がったり骨の量が減ってしまったりすることがあります。
「通う手間」よりも、「長持ちする安心感」を大切にすることがポイントです。
歯医者と自宅ケアの二本柱が大切
インプラントを長く保つには、歯医者でのプロフェッショナルケアと、毎日のホームケアの両立が欠かせません。
歯医者では、専用の器具で汚れを除去し、噛み合わせや歯ぐきの状態を確認します。
一方、自宅ではブラッシングや歯間ブラシを使って汚れをためないようにします。
この「医院」と「自宅」のダブルケアが、インプラントを守るいちばんの秘訣です。
自宅でできる!毎日のインプラントケア方法
①歯ブラシ選びと磨き方のコツ
毛先が細いソフトタイプでやさしく磨く
インプラントの周囲は、天然歯よりもデリケートです。
硬い毛のブラシでゴシゴシ磨くと、歯ぐきを傷つけてしまうことがあります。
そのため、毛先が細くて柔らかい歯ブラシを使い、力を入れすぎずにやさしく磨くのがおすすめです。
歯ぐきとの境目を意識して汚れをためない
インプラントの清掃で特に大切なのが、歯と歯ぐきの境目です。
この部分に汚れが残ると、細菌が増えて炎症を起こしやすくなります。
ブラシを歯ぐきに45度の角度で当て、細かく小刻みに動かすように磨くのがコツです。
慣れるまでは鏡を見ながらゆっくり行うのがポイントです。
焦らず丁寧に磨くことが、インプラントを守るいちばんの近道です。
②補助用具を活用して細部までケア
歯間ブラシ・フロス・タフトブラシの使い分け
歯ブラシだけでは、インプラントの周りの汚れをすべて落とすのは難しいです。
そこで役立つのが、歯間ブラシやフロス、タフトブラシ(先が小さいブラシ)です。
「最初は難しそう」と感じる方も、実際に一緒に練習するとすぐに慣れていくので、歯医者で使い方を確認しながらの導入がおすすめです。
夜のケアを丁寧にすることで炎症予防に
特に意識してほしいのは、夜のケアです。
寝ている間は唾液が減って細菌が増えやすくなるため、就寝前の清掃がとても大切です。
一日の終わりに丁寧にケアしてあげることで、歯ぐきが落ち着き、朝のネバつきも減ります。
実際に「夜のフロスを習慣にしたら歯ぐきが引き締まってきた」と喜ばれる患者さんも多いです。
③生活習慣もインプラントの寿命に影響
喫煙や糖尿病がある場合は注意
喫煙や糖尿病は、インプラントの成功率や持続年数に影響する要因です。
タバコに含まれるニコチンは血流を悪くし、歯ぐきの回復を遅らせます。
また、糖尿病の方は炎症が起きやすく、治りにくい傾向があります。
私の経験でも、禁煙や血糖コントロールを行った患者さんのほうが、長く安定して使えているケースが多いです。
免疫を整える生活リズムを意識
睡眠不足やストレスも、免疫力を下げて炎症の原因になります。
バランスの良い食事や適度な運動を意識し、「体の健康=お口の健康」として考えることが大切です。
お口のケアは、全身のケアにもつながっています。
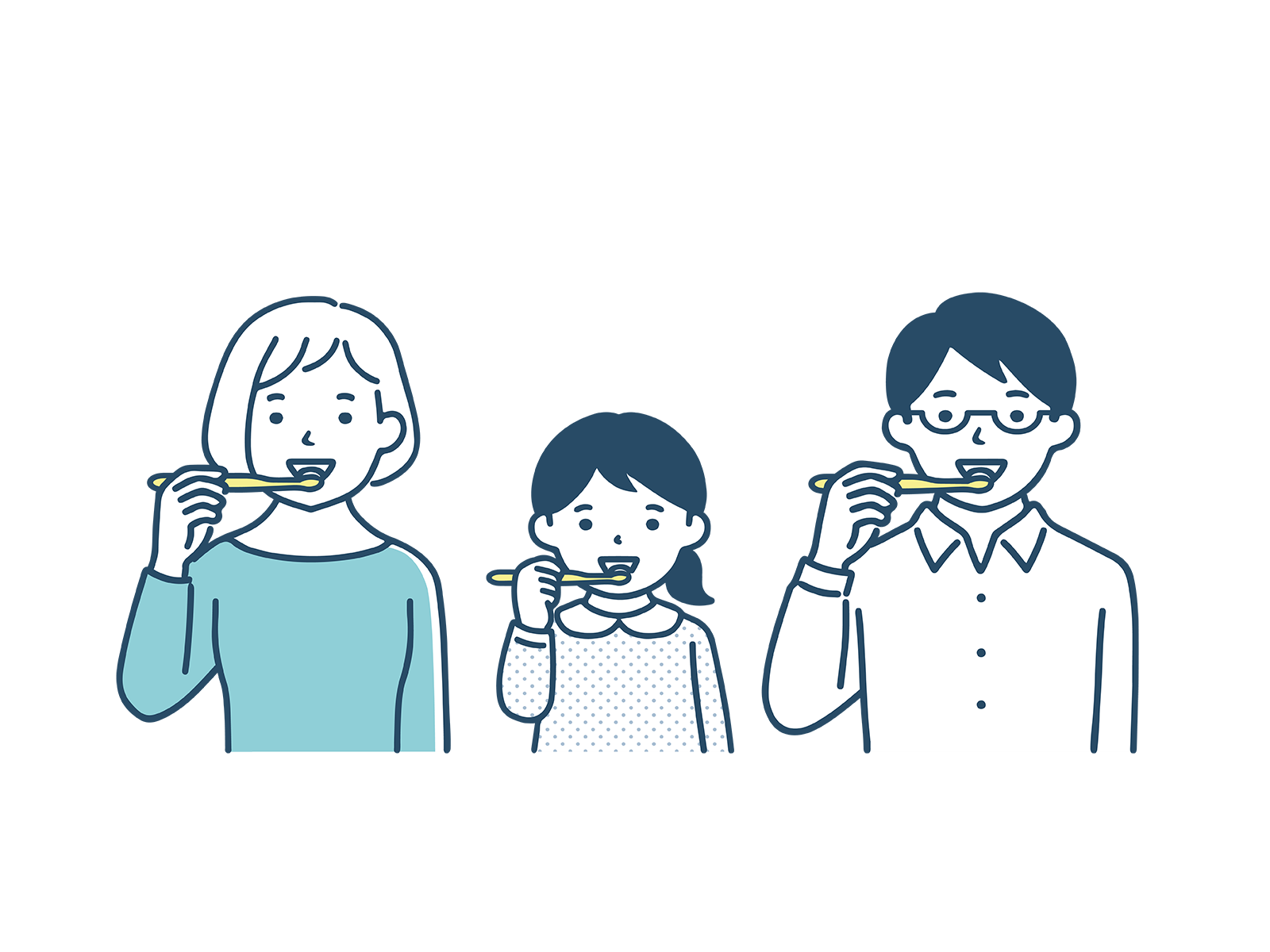
歯医者でのプロフェッショナルメンテナンス
①定期検診でチェックする3つのポイント
歯ぐきの状態(出血・腫れ・歯周ポケット)
まず確認するのが、歯ぐきの健康状態です。
歯ぐきに出血や腫れがないか、インプラントのまわりに深い歯周ポケット(すき間)ができていないかをチェックします。
歯周病と同じように、初期の炎症を見逃さないことが大切です。
「自分では痛みもないけど、実は少し炎症が進んでいた」というケースもあるため、プロによる定期チェックは欠かせません。
インプラント周囲の汚れ・噛み合わせの確認
歯医者では、専用の器具でインプラントの周りの汚れを丁寧に取り除きます。
同時に、噛み合わせのズレや力のかかり方もチェックします。
噛む力が一点に集中するとインプラントや骨に負担がかかってしまうため、細かな調整を行うこともあります。
レントゲンで骨の変化をチェック
半年〜1年ごとにレントゲンを撮影し、あごの骨の状態を確認します。
骨の吸収や炎症の有無を早期に見つけることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
レントゲン検査は短時間で済み、被ばく量もごくわずかです。
「痛みが出てから行く」よりも、「何もないうちに確認する」ことが、インプラントを守る最大のポイントです。
②専用器具による安全なクリーニング
金属を傷つけないチタン専用器具で清掃
インプラントの素材であるチタンはとても繊細で、金属製の器具で強くこすると表面に傷がつくおそれがあります。
そのため、歯医者ではチタン専用のプラスチックや炭素繊維の器具を使って、安全に汚れを除去します。
この専用クリーニングによって、インプラント表面を傷つけずに清潔に保てます。
患者さんごとのリスクに応じたメンテ内容
メンテナンス内容は、患者さんの状態によって少しずつ変わります。
たとえば、喫煙されている方や糖尿病の方は炎症のリスクが高いため、より丁寧な清掃や短い間隔での通院をおすすめすることもあります。
私自身、患者さんごとにブラシや歯間ブラシのサイズを選び、一緒に練習するようにしています。
「自分のケア方法を知ること」も、立派なメンテナンスの一部です。
③通院頻度の目安とメンテナンスの継続
基本は3〜6か月ごとのチェック
多くの方は、3〜6か月ごとの定期メンテナンスを目安に通院しています。
「そんなに頻繁に?」と思う方もいらっしゃいますが、その分トラブルの早期発見が可能です。
実際、トラブルが起きる前にケアを続けている方ほど、10年以上問題なくインプラントを維持されています。
トラブルが起きる前に「予防の通院」を
痛みや腫れが出てからの受診では、すでに症状が進んでいることが多いです。
「異常がなくても定期的に見てもらう」ことこそが、インプラントを守る最大の予防です。
その積み重ねが、インプラントを長く使えることにつながります。

まとめ
インプラントは「入れたら終わり」ではなく、「入れてから育てていく歯」です。
日々のケアと定期的なメンテナンスを続けることで、10年、20年と快適に使い続けることができます。
毎日のケアを習慣にし、数か月ごとのメンテナンスを続けていきましょう。
もし腫れや違和感を覚えたときは、自己判断せず、早めに歯医者でチェックを受けてください。
きちんとお手入れをしてあげることで、インプラントは毎日の食事や笑顔をしっかり支えてくれます。
この記事を監修した人

医療法人社団周優会
常務理事 笠原幸雄所属学会
東京シティー日本橋ロータリークラブ会員
お江戸日本橋歯科医師会選挙委員会 委員長
一般社団法人 日本橋倶楽部会員
東京科学大学歯学部 東京同窓会参与略歴
私立開成高校卒業
早稲田大学理学部卒業
東京医科歯科大学歯学部卒業
東京医科歯科大学病院勤務
笠原歯科医院 蔵前開設
医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 人形町開設
医療法人社団周優会 日本橋グリーン歯科 常務理事
医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 六本木開設
