デンタルニュース
歯ブラシを濡らすのはNG?今日から見直せる3つの衛生習慣
日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。
患者さんからよくいただく質問のひとつに、「歯ブラシは水で濡らしてから使ったほうがいいの?それとも乾いたままが正解?」 というものがあります。
近年はSNSやネット記事でも「濡らさない方がいいらしい」と話題になることがあり、いつもの習慣に不安を覚える方も増えている印象です。
実際に診療室でブラッシング指導をすると、約半数以上の方が「何となく濡らしていた」と答えます。中には「今までずっと濡らして使っていたけど、これって不衛生ですか?」と不安そうに聞かれる方もいます。
そこで今回は、「歯ブラシを濡らす・濡らさない」の問題を切り口に、毎日のブラッシングを衛生的に保つためのポイントをご紹介します。
すぐに実践できることなので、今日からさっそく生活に取り入れてみてください。
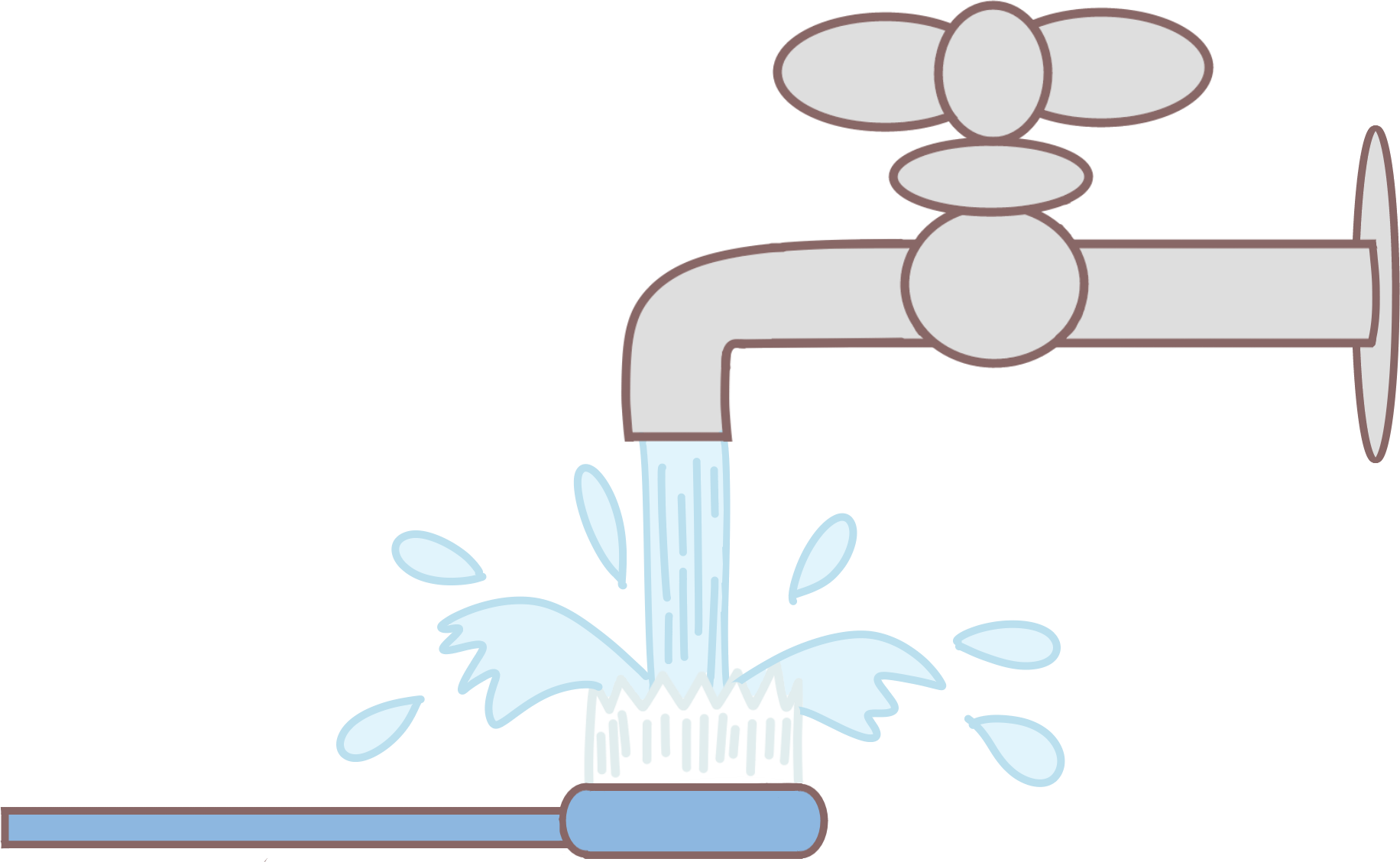
歯ブラシを濡らす前に知っておきたい誤解
①濡らすと「泡立ちがよくなる」は本当?
泡立ちすぎが磨き残しにつながるリスク
多くの方が「歯ブラシを濡らすと泡立ちやすいから」と、つい蛇口の水でサッと濡らしてから歯磨き粉をつけています。
確かに、濡らすことで泡立ちは良くなります。しかし、泡立ちが良すぎると「もう十分磨けた」と感じやすく、実際には磨き残しが出ることもあるのです。
磨き残しはむし歯・歯周病の菌にとって温床になりやすいので、磨き残しが出ないようにできるだけ効果的な方法で習慣化することが大切です。
泡に頼らず、鏡でチェックしながら時間をかけて丁寧に磨くことが、虫歯や歯周病を防ぐ近道です。
歯磨き粉の薬用成分が薄まる可能性も
歯磨き粉に含まれるフッ素や殺菌成分は、水で薄まると効果が弱まることがあります。
特にフッ素は歯の表面に長くとどまることで初めて虫歯予防効果を発揮します。
そのため、歯ブラシは乾いた状態で歯磨き粉をつける方が薬効を最大限に活かせる場合があります。
私も患者さんには「まずは乾いたブラシで始めて、最後のうがいは1回だけにすると、フッ素がしっかり歯に残りますよ」とお伝えしています。
②「濡らさないとゴワゴワする」は間違い?
乾いたブラシの方がプラーク除去力が高い場合も
「濡らさないと毛先が硬くて痛い」と感じる方もいますが、乾いたブラシは毛先がしっかりと歯面に届くため、プラーク除去効果が高まることがあります。
ゴワつき対策は歯ブラシ選びで解決
歯ブラシを濡らさない場合のゴワつきが気になる場合は、毛先が細いタイプややわらかめのものを選ぶのがおすすめです。
また、使い始めの歯ブラシは少し毛が硬い場合もあるので、気になる方は最初の1〜2回だけ軽く湿らせるなど、自分に合った方法を見つけるのが大切です。無理のない範囲で取り入れてみましょう。
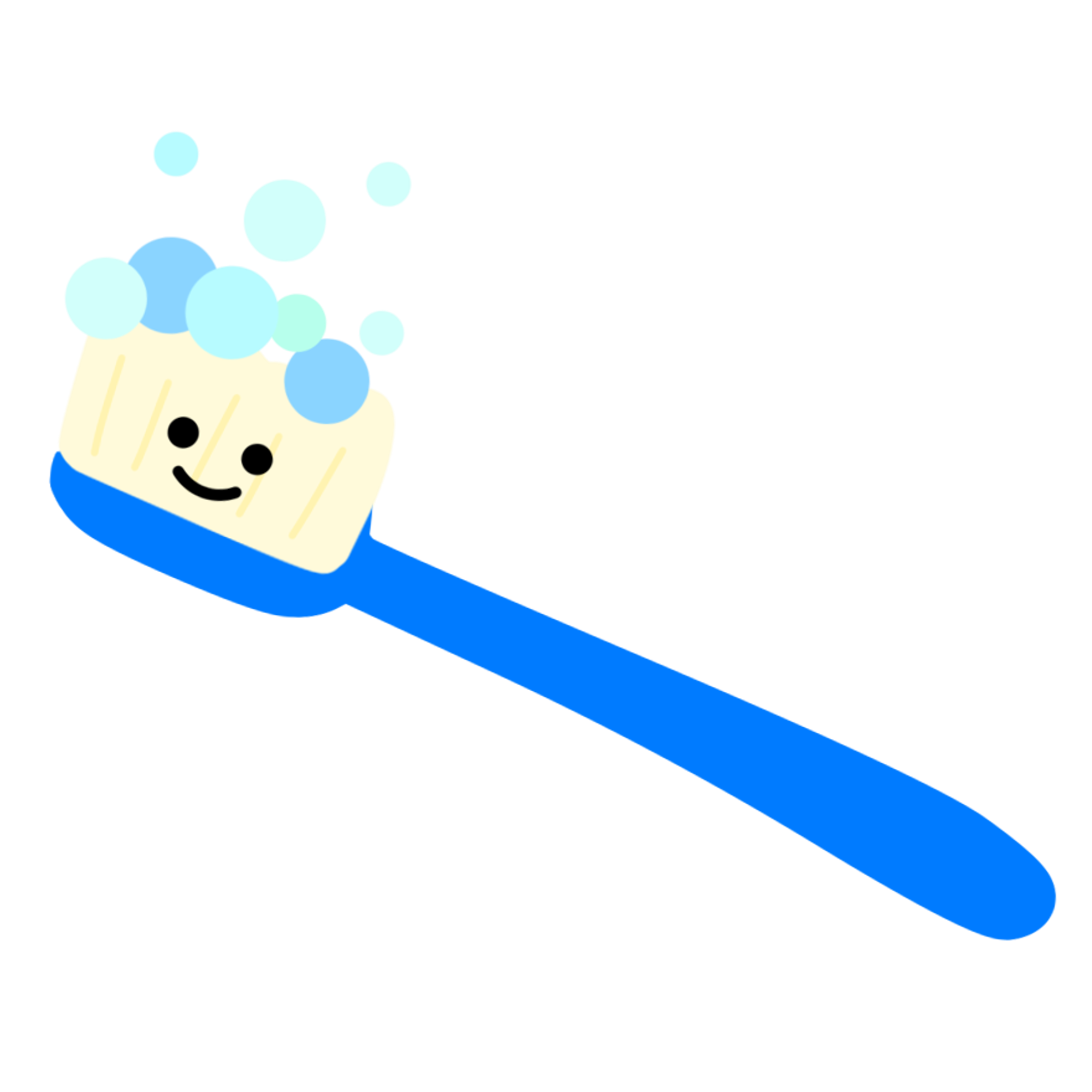
歯ブラシを清潔に保つための対策
①使った後のすすぎ方で菌の増殖を防ぐ
根元まで流水でしっかり洗う
歯磨き後は、歯ブラシの毛先だけでなく根元までしっかり流水で洗いましょう。
指で軽くこすりながらすすぐと、歯磨き粉の残りや食べかすを落としやすくなります。
患者さんに使用している歯ブラシを持ってきてもらうと、根元に白いカスがこびりついた歯ブラシをよく見かけます。
これは乾いた歯磨き粉やプラークが固まったもので、使い続けると細菌の温床になってしまいます。
水気を飛ばすひと手間で雑菌繁殖を防ぐ
洗った後は、軽く振って水分を飛ばしたり、タオルでトントンと叩くとさらに清潔です。
水分が残ったままだと雑菌が繁殖しやすく、口に戻すたびに細菌を運ぶことになってしまいます。
②保管方法で清潔度は大きく変わる
湿気の多い場所で保管しない工夫
歯ブラシの保管場所も大事なポイントです。
浴室内に置いている方もいますが、浴室内は湿気がこもりやすく細菌やカビの温床になりがちです。
可能であれば、通気性の良い場所にブラシ部分を上にして立てて保管してください。
コップよりも立てて乾燥、除菌ケースも活用
コップに毛先が下向きになるように突っ込んでいる場合は、水が溜まって雑菌の原因になるので避けましょう。
コップに立てる場合は、毛先が乾きやすいように上に向けて立てる必要があります。
最近ではUV除菌機能付きの歯ブラシスタンドも人気です。毎回乾かすのが難しい方や、湿度の高い場所に住んでいる方にはおすすめです。
洗面所の湿度と歯ブラシの劣化リスク
家庭の洗面所は意外と高温多湿で、換気が不十分だと菌にとって理想的な環境になります。
長く置くと目に見えないカビや細菌が付着するリスクがあるため、乾燥と換気を意識しましょう。
換気扇を回していない・歯ブラシを密閉したケースに入れたまま保管しているといった状態では、カビが発生する可能性もあります。
見た目はきれいでも、細菌が大量に付着している歯ブラシを口に入れていることになるため要注意です。
家族内で間違ってしまわないよう一目でわかるデザインを
「家族の歯ブラシを間違って使ってしまった…」という経験がある方もいらっしゃるかもしれません。たとえご家族であっても、歯ブラシの共有は絶対に避けてください。
お口の中には、誰にでも約700種類以上の細菌が存在しています。これらの細菌は、虫歯菌や歯周病菌など、お口のトラブルを引き起こす原因菌も含まれています。
歯ブラシを共有すると、これらの細菌が唾液を介して簡単に移ってしまいます。特にまだ抵抗力の低いお子さんや、高齢のご家族がいる場合は注意が必要です。
歯ブラシは家族一人ひとりが自分のものを持つようにし、一目で区別できるような色やデザインのものを選ぶのがおすすめです。
③歯ブラシは“消耗品”!交換目安を守る
月1回の交換で衛生的に
歯ブラシは使用を重ねると毛先が広がるだけでなく、細菌も蓄積していきます。
見た目がきれいでも、1か月に1本を目安に交換すると安心です。
毛先の開きだけでは判断できない
「毛先が開いたら交換」と思っている方も多いですが、開いていなくても細菌は増えます。
特にお子さんは歯ブラシを噛んだりすることが多いため、毛が早く劣化します。家庭でも定期的にチェックしてあげてください。
電動歯ブラシの「替えブラシ」の交換タイミング
電動歯ブラシは、手磨きよりも効率的にプラークを除去できる便利なアイテムです。
しかし、本体だけでなく「替えブラシ」の衛生管理も重要です。
替えブラシも手用歯ブラシと同様に、使用を重ねるごとに毛先が劣化したり、細菌が蓄積したりします。
一般的には約3か月ごとの交換が推奨されています。毛先が開いていなくても、ブラシの奥には汚れがたまりやすく、除去効率も落ちてしまうからです。
また、使用後はブラシ部分を本体から外し、流水で根元までしっかり洗浄してください。
洗浄後は風通しの良い場所でしっかり乾燥させることで、より清潔な状態を保てます。
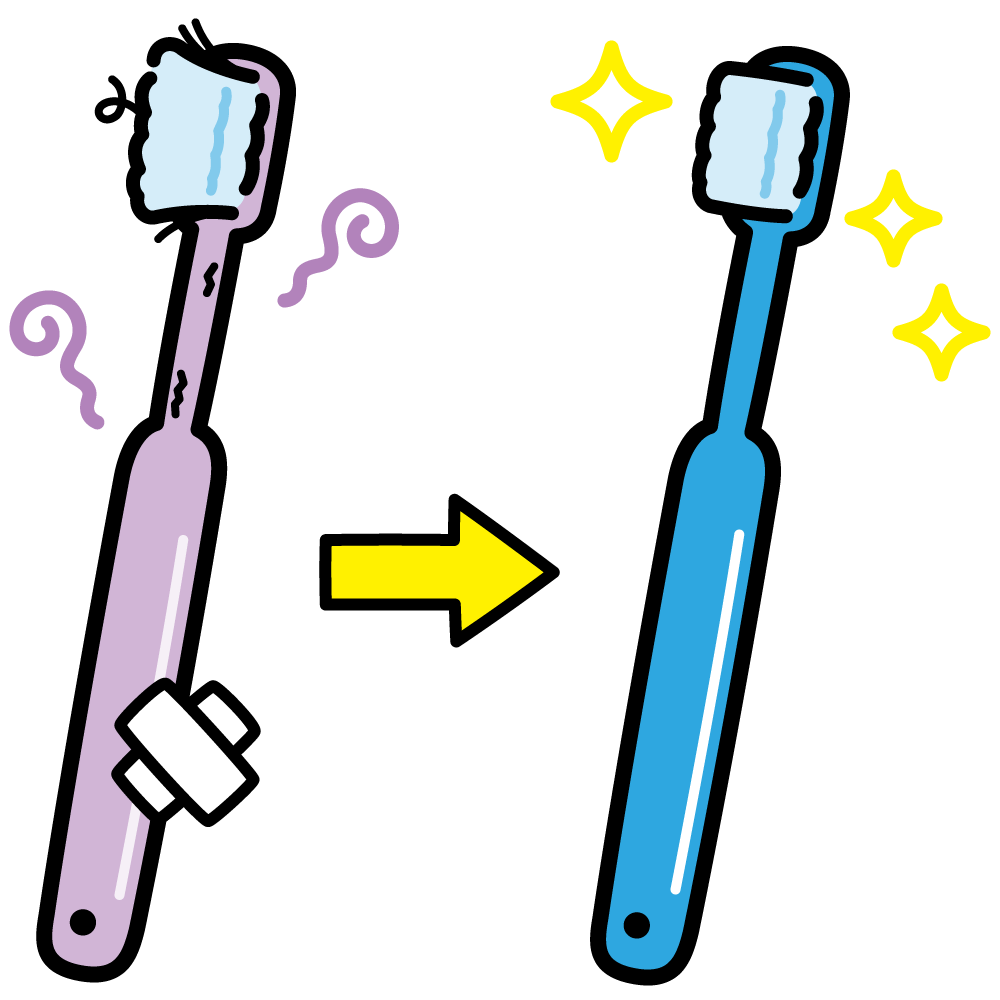
まとめ
歯磨きの際には、磨き残しのリスクや歯磨き粉の成分の有効活用のためにも、歯ブラシを濡らさないで使用することがおすすめです。
そして歯ブラシは毎日使うものだからこそ、濡らす・濡らさないだけでなく「正しい使い方」「清潔な保管」「定期的な交換」がとても大切です。
なんとなくではなくしっかり理由を持って使うことが、口腔ケアの質を高めます。
ちょっとした意識の変化が、虫歯や歯周病の予防につながります。
今日からぜひ、ご自身の歯ブラシ習慣を見直してみてください。
この記事を監修した人

医療法人社団周優会
常務理事 笠原幸雄所属学会
東京シティー日本橋ロータリークラブ会員
お江戸日本橋歯科医師会選挙委員会 委員長
一般社団法人 日本橋倶楽部会員
東京科学大学歯学部 東京同窓会参与略歴
私立開成高校卒業
早稲田大学理学部卒業
東京医科歯科大学歯学部卒業
東京医科歯科大学病院勤務
笠原歯科医院 蔵前開設
医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 人形町開設
医療法人社団周優会 日本橋グリーン歯科 常務理事
医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 六本木開設