デンタルニュース
よく噛むことで得られる効果
本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。
「よく噛むこと」が大事だと聞いたことがある方は多いと思います。
でも実際に「なぜ大事なのか?」「どんなメリットがあるのか?」までは、意外と知られていません。
特にビジネスパーソンの方は、仕事の忙しさから早食いやながら食いが習慣化していることも多く、それが体調や集中力に影響しているケースもあります。
この記事では、よく噛むことで得られる効果と、噛む習慣を増やすためのポイントについて解説します。
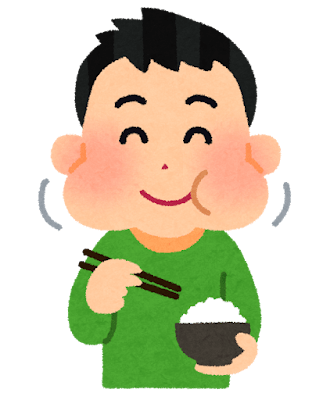
よく噛むことで変わる3つの健康効果
ここでは、よく噛むことによって得られる健康効果を3つ解説します。
いずれも忙しい働き世代の方にこそ取り入れてほしい効果なので、ぜひ参考にしてみてください。
①よく噛むことでダイエット効果
噛む回数とカロリー消費の関係
よく噛むことであごの筋肉を使い続けるため、カロリーの消費など全身の代謝にも影響が出ます。
ある研究では「1口30回噛む」習慣を持つ人は、噛む回数が少ない人に比べて体重が増えにくい傾向があるという結果が出ています。
満腹感を得やすい
噛む回数が増えると、脳の「満腹中枢」が刺激され、満腹感を感じやすくなります。
よく噛むことで食事量が自然と減り、無理な我慢をせずに食べ過ぎを防ぐことができるのです。
早食いの方は満腹感を感じる前にどんどん食べてしまうため、たくさん食べてしまいがちです。
時間に追われがちなビジネスパーソンこそ「時間をかけて食べる」ために噛む回数を意識することが大切です。
②よく噛むことで集中力アップ
血流促進と脳神経への影響
噛むことには「脳を目覚めさせる」効果もあります。
噛むことによってこめかみの筋肉が動くと脳へ血液が送られやすくなり、脳の集中力や判断力、意欲を司る部位が活性化します。
特に朝の食事でしっかり噛む習慣を持つと、その日1日の仕事の立ち上がりがスムーズになります。
集中力を保つための噛む習慣
集中力が途切れやすい午後や、単調な作業が続く時などにはガムを噛むことも効果的です。
噛むことによるリズムは自律神経を整える効果もあるため、ストレス軽減の効果も期待できます。
忙しい中でも手軽に取り入れられる、脳へのスイッチとしておすすめです。
③良く噛むことで胃腸の負担を減らす
唾液分泌の促進と消化酵素の働き
唾液には消化を助ける酵素が豊富に含まれており、食べ物を消化しやすい状態にしてくれます。
よく噛むことで唾液の分泌が増え、食べ物が口の中でしっかりと分解されてから胃に運ばれるため、胃の負担が軽くなります。
胃腸への負担軽減
胃や腸への負担が軽減されることで、食後の眠気やだるさも抑えられ午後の仕事のパフォーマンス維持にもつながります。
また、胃腸の調子が整うと、免疫力アップや肌荒れ改善といった美容面の効果も出やすくなります。
働き盛りの方にとって、体調を崩さず安定して働けることは何よりのパフォーマンス強化になります。噛むだけでそれを助けられるとしたら、試さない手はありません。

噛む習慣を増やすポイント
よく噛むことの効果はわかっても、実際に毎日の生活に取り入れるのはなかなか難しいですよね。
しかし、噛む習慣は「意識」と「ちょっとした工夫」で自然と身についていくものです。
ここでは、私が歯科衛生士として患者さんに実際におすすめしている方法をご紹介します。
①噛み方を変える
ゆっくり噛むことで満腹感を得るコツ
忙しいと食事を早く済ませたい気持ちはわかりますが、実はゆっくり噛んで食べることが結果的に午後の仕事の効率を上げてくれるのです。
早食いをすると血糖値が急上昇し、反動で眠気やだるさを引き起こすことがあります。よく噛むことで血糖値の急上昇を防ぎ、食後のパフォーマンスが安定します。
歯科衛生士の私が指導する際、まずおすすめしているのは「ひと口につき20〜30回を目標に噛む」ことです。最初は数えながらでも構いませんが、習慣化すると数えなくても自然と噛む回数が安定してきます。
噛む回数を意識する習慣づくり
少しの工夫で、噛む回数を意識しやすくすることはできます。
「食事の最初の3口だけは30回噛む」「固い食材(根菜、玄米、ナッツなど)を意識的に取り入れる」「お茶や水で流し込まずに唾液で飲み込むことを意識する」などが取り入れやすくおすすめです。
②ガムや噛みごたえのあるおやつを摂る
仕事中におすすめの噛むアイテム
食事以外の場面でも、噛む習慣をサポートしてくれる方法があります。それが無糖ガムや噛みごたえのあるおやつの活用です。
特に午後の時間帯や集中が途切れがちな会議前など、ガムを噛むだけでも脳がシャキッとします。私の患者さんでも、営業職やエンジニアの方が「午後は必ずキシリトールガムを噛む」と習慣化している方がいらっしゃいました。
おすすめのおやつのポイント
おやつを選ぶ際のポイントは「無糖」「キシリトール配合」「噛みごたえがある」ものを選ぶことです。
この条件に当てはまるおやつを選ぶことで、歯に優しい上に噛む刺激がしっかり得られます。
③噛む回数の目安を知る
1回の食事での理想的な噛む回数とは?
理想は、ひと口あたり30回です。これだけ噛むと自然と食事時間が20分〜30分になり、満腹中枢もしっかり働きます。
自然に数える習慣づくりのポイント
「いちいち数えるのは大変…」という方には、噛む必要のあるごはんを用意するのがおすすめです。
「雑穀米や玄米を取り入れる」「生野菜を細かく刻まずに食べる」「よく噛まないと飲み込めない食材を選ぶ」など、食材を少し工夫するだけで自然と噛む回数が増える食事環境をつくることができます。
④噛む習慣の生活リズムと工夫を作る
食事の時間を5分伸ばしてみる
最初から「30回噛むぞ!」と意気込むよりも、食事時間を5分長くするくらいの意識から始める方が現実的です。
実際に、お仕事が多忙な方にとっては5分のゆとりが非常に大きな差になります。
例えば、朝食を立ったまま食べている場合は椅子に座って5分ゆっくり食べるようにしたり、昼食が10分で終わっていた場合は15分を目標にしてみるなど、簡単なことから始めてみましょう。
食事に余裕が生まれると、自然と噛む時間も取れるようになります。
目に見える場所に「噛むリマインダー」を置く
噛むことを忘れがちな方には、目に見えるリマインダーの活用がおすすめです。
たとえばデスクや冷蔵庫に「ひと口30回!」と貼り紙をしたり、時間になったらお知らせが鳴るようにスマホのアラーム機能を利用したりと、さりげない工夫が意識づけに役立ちます。 習慣化とは、少しの繰り返しの積み重ねです。

噛み合わせ・歯並びの悪化防止のポイント
歯科衛生士として現場にいると、「いつの間にか前歯がズレてきた」「顎がガクガクするようになった」といった相談を受けることがよくあります。
ここでは、歯並び・噛み合わせを守るために、日常生活で注意すべきポイントをご紹介します。
①姿勢の悪さによる影響
スマホ首・猫背と顎の位置の関係
現代人に多い「スマホ首」や「猫背」は、見た目だけでなく顎の位置や噛み合わせにも大きく影響します。
姿勢が悪いと首や肩に余計な力が入るため、下顎が本来の位置からズレやすくなるのです。その結果、片方の歯だけが強く当たったり、顎関節に負担がかかったりすることもあります。
デスクワーク中の正しい姿勢
日常的にできる予防策としては、「モニターの高さは目線と同じくらいにする」「背筋を伸ばし、骨盤を立てるように座る」「30分に1回、首や肩を軽く回してリフレッシュする」などがあります。
姿勢が整うと、噛み合わせも安定しやすくなります。歯や顎に不調が出てきたときは、まず座り方やスマホの見方から見直してみましょう。
②片側噛みによる影響
片側ばかりで噛んでしまうクセ
意外と多いのが、「片側だけで噛む」クセです。
これを長く続けると、あごの筋肉のバランスが崩れ、左右の歯の位置も変化してしまうことがあります。
片噛みは「奥歯に物が詰まりやすい」「顎がカクカク鳴る」「片側の頬だけ疲れる」といった症状で気づくこともあります。
左右バランスを意識した食事の取り方
癖を治すには、自身の噛み癖を自覚するところから始めます。
食事中に「どちらで噛んでいるか」を1週間だけでも記録してみると、自分のクセに気づけることがあります。
もし自分が片側噛みばかりしていると気づいたら、毎日の食事から変えていきましょう。
最初のひと口は左、次は右、と意識して交互に噛むんでみてください。慣れてくると意識しなくてもバランスよく左右使えるようになります。
③歯医者での定期チェックの重要性
噛み合わせは変化する
歯並びや噛み合わせの変化は、少しずつ進行するため気づきにくいのが特徴です。
「なんとなく噛みにくい」「以前より食べ物が引っかかる」といった違和感があれば、早めの検査が大切です。
半年〜年1回の定期検診を受けることで予防にも早期治療にもつながります。
噛み合わせチェックでの確認
定期検診では、「咀嚼の左右バランス」や「歯の擦り減り具合や噛み合わせのズレ」などが確認できます。
私たち歯科医療従事者も、患者さんの生活背景を伺いながらできるだけ無理なく続けられるアドバイスを心がけています。
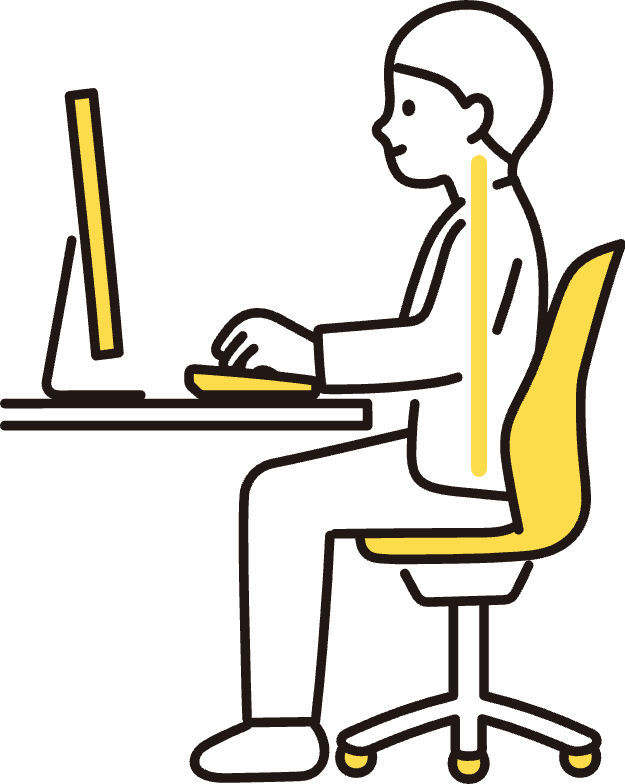
まとめ
「よく噛むこと」は健康維持だけでなく、仕事の集中力やストレス管理、さらには美容にも直結する健康習慣です。
まずは今日の食事から「ひと口多く噛む」「食材を変える」といった小さな一歩を踏み出してみましょう。
この記事を監修した人

医療法人社団周優会
常務理事 笠原幸雄所属学会
東京シティー日本橋ロータリークラブ会員
お江戸日本橋歯科医師会選挙委員会 委員長
一般社団法人 日本橋倶楽部会員
東京科学大学歯学部 東京同窓会参与略歴
私立開成高校卒業
早稲田大学理学部卒業
東京医科歯科大学歯学部卒業
東京医科歯科大学病院勤務
笠原歯科医院 蔵前開設
医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 人形町開設
医療法人社団周優会 日本橋グリーン歯科 常務理事
医療法人社団寿幸会 笠原歯科医院 六本木開設